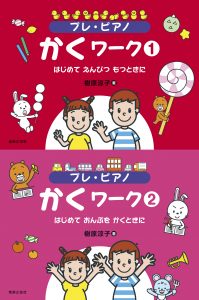『プレ・ピアノ かくワーク①② 発刊記念セミナー』レポート
この夏、初めてのワークブックを出版しました!
その、『プレ·ピアノ かくワーク①② 発刊記念セミナー』レポートを、
ライターの豊永泰子さんに書いてもらいました。
とても楽しいレポートなので、じっくりご覧ください! 樹原涼子
『プレ・ピアノ かくワーク①② 発刊記念セミナー』レポート 文:豊永泰子
ピアノランドフェスティバル2025「樹原先生と小原君の爆笑レッスン」でお目見えした「プレ·ピアノ かくワーク①」『プレ・ピアノ かくワーク②』発刊記念セミナー、カワイ表参道に行って参りました!
「かく」についてみっっっっっちり120分間に詰め込まれたこのセミナー、使われたスライドは怒涛の117枚、実際に3歳児ちゃんが「かく」動画も多数、樹原先生はかつてないほどの早口で、疾走感に溢れ、カロリー消費量が多いセミナーでした。
最近お二人での出演が多くなりました、作曲家で次男の樹原孝之介さんとの楽しいトークが繰り広げられました。
「利き手」について考える1巻
まずは「利き手」の概念について考えることから始まります。右利き、左利き、そして交差利きについて。交差利きというは、両利手利きとは違い、場合によって手を使い分けることだそうです。帰宅して調べましたら、英語ではクロスドミナンスという、かっこいい必殺技のような名称でした。現代は9:1で右利きの人が多いようですが、250万年前(石器時代)は4割の人が左利きだったそうです。というわけで(?)、右利き、左利き、両方を平等に扱うこの本、最初に手の左右と指番号を教えたあと、「鉛筆の持ち方」では、左右両方の鉛筆の持ち方の絵が、3歳児と同じ手の大きさで!子どもから見た目線そのままのイラストで!!描かれているのです。そしてそのページには、鉛筆の持たせ方の解説動画(QRコード)付き。最近のこどもは動画を見慣れているので、おとなとこどもが同じ向きで一緒に並び、動画を見ながら持ち方を学ぶ方がわかりやすいそうです。
いざ、書くのは?
そして次のページからは、「にょろにょろをかこう!」「まるをかこう!」さらに、まるの発展形である「おだんごをかこう!」「めだまやきを(以下略)」「どーなつ(略)」と、美味しい食べ物を書こうシリーズになっています。なるほどね。これは美味しいものを書いているうちに音符も書けるようになるってこと?と顔がニヤニヤしてしまいます。続いて、「まっすぐ」「うねうね」「ぎざぎざ」「でこぼこ」(これはドの横棒や桁、五線を書く準備?)、「しかく」「さんかく」「おばけのめいろ」(メロディーラインをきちんと綺麗に結ぶのに必要だよね~)と、本当に楽しく、お勉強っぽさはひとかけらも感じさせずに進んでいきます。「おばけ」にはかわいい絵描き歌もありますので、ハロウィンに向けて、歌いながらたくさんおばけを書くのも楽しいかも!
こうしてたくさん線を書いたあとに、あらためて左右を確実に覚えたかどうか確認するページがあります。クイズも交えて、ゆっくり、しっかり、確実に。こどもによっては、左右の認識がいつまでもあやふやになることがあるので、最初の段階でしっかり覚えられるようにしましょうとお話しされていました。
数を学ぶページ
線が思った通りにかけるようになったら、次は数について。音楽(楽譜)は数と密接な関係にあります。世の楽典の本をご覧になって分かる通り、テンポ記号の他にも四分の四拍子、八分音符、減三和音などなど、あちこちに数字が使われています。
このワークブックではアラビア数字にふりがなが振ってあり、例えば「4」は「よん」「し」、「7」は「なな」「しち」と、2種類の読み方がある数字も漏らさず書かれています。大人になった今では当たり前のように数を読んでいますが、初めて数字に出逢うこどもにとっては知らないことばかり。「なな」も「しち」も同じ「7」だよと、易しく教えてくれます。
さらに、左から右に数字が等間隔に配置され、数がだんだん「増える」感覚も直観的に感じられるようになっています。また、数字に使われている字体は「6」と「9」の形がはっきりと違う教育用フォントというこだわりも。子どもは文字の左右や上下を反転して見ることがあるので、形がはっきり違うとわかるフォントを選択したそうです。教科書と同じ字体なので、学校で教科書に出逢った時に嬉しくなるかもしれませんね。
「◯」から、「音符」への橋渡し
たっぷり線や図形を書き、数の数え方も馴染んだ「かく ワーク①」の終わり頃になると、いよいよ五線に音符っぽいまるを書き始めますが、まるの中に顔を書いたりと、まだまだ楽しい時間は続きます。楽しいけれど、間の音符は線と線の間にぴったり収まるように、線の上に書く「おだんご」は上下の空間に制限がないので、書くのはちょっと難しいから慎重に大きさを考えてと、綺麗に書けるように、ちょっとだけ手伝いながら見守ります。
音符を書き始める 2巻
実際に「楽譜」が登場するのは「かく ワーク」②からです。「ヘ音記号は、書き始めの「黒い丸」にエネルギーをこめてから、ぐる~っと!」と説明する樹原先生の楽しそうなこと! 二つの点は、耳飾りですと!
そして「せん」「かん」とすすみ、「ド」が書けたら「どどどど どーなつ」の楽譜を書くページに続きます。「レ」が書けたら「ぴかぴかぼし」のぴかぴかきらきらパートが書ける!「シ」が書けたらお腹がすいたあの曲が書ける!
「ミ」以降はおとなと一緒にみかん色や空色を使って、プレ·ピアノランドと同じように線や間を塗ります。自分が書いた楽譜と、習う楽譜が同じ! 今わたしがピアノで弾いているこの曲、書いたことあるよ!と、再発見したら嬉しいよね~と、またもやニヤニヤ。
楽譜の書き方も、ていねいに、美しく。綺麗に書くために、音符に棒を引く時に、自然に長さを揃えたくなるように工夫されています。音符を書く時は必ずその音を歌いながら、あるいは先生がその音をピアノで弾きながら。その音の高さに浸りながら書くことが重要。
そして、何から何まで先回りして教えこむのではなく、四分休符や付点など「これな~に?」と、こどもが見つけたら、よく見つけたね~!と教えてあげる。こどもの好奇心や気づきを大切にというお話しに、丁寧と過保護の違いを考えてレッスンしないといけないと思いました。
忘れないでほしい、「観察する」こと
子どもが「かく」ことに出逢うこのワークには、すみずみまで行き届いた工夫が施されていますが、何より大事なのは先生(おとな)の向き合い方です。樹原先生が繰り返し仰っていたのは「こどもと一緒に書いて、子どもの様子をよく観察すること」「生徒を観察することが大事なの。」ハイこれ宿題ね、家でやってきてねと渡さないでくださいと。
書くことは、生きること?
そしてさらに重要なのは、「かく」とはどういうことなのかということ。書くことは考えること、生み出すこと、伝えること、自分を生きること。
音楽でも絵でも、何かに感動すると自分でも作りたくなる。それに、こどもの頃を思い出すと、色鉛筆を選ぶ時、わくわくしたでしょ?新しいまっさらなノートって嬉しくなかった?とお話しされるのを聞き、首をぶんぶん縦振りする私。幼稚園で使う新品のクレヨンの艶と、巻いた紙がとても綺麗だと思ったこと。自分のよりたくさんの色が詰まっていた絵画教室のクレヨンを見てびっくりしたこと。わら半紙に絵本に描かれていた鳥の絵を夢中になって写し書きしていたことなど、50数年前の記憶がブワッと蘇りました。
こどもに備わっている原初的な喜びである「かく」ことを、正しい鉛筆の持ち方を覚えることで上手に扱えるようになり、書くことの大変さが楽しさに変わりますように、という祈りを込めた「かくワーク①②」。これからの二段階導入法は「聴く 歌う 動く 見る 書く」になります!と樹原先生が宣言した通り、この「かくワーク」は必修です。「かくワーク①」→「プレ·ピアノランド①」→「かくワーク②」→「プレ·ピアノランド②」と進めると良いそうです。
私の大きな悩みが一つ、解決する予感
ところで実は、もうずっと悩んでおりました。おそらくは10年以上前からになると思いますが、子ども達の鉛筆の持ち方が壊滅的に下手になっていることに。書いている様子を観察すると、1の指がまっすぐに伸びて他の4指はグーで握り込み、2と3の指の間に鉛筆を「刺した」状態でモゴモゴといった様子で手を動かして字を書いている。握り込んだ自分の手に隠れて字が見えないから、鉛筆の先を見るために体を斜めにする。正しい持ち方を教えると、1の指の付け根がへこんで力が指先に向かってうまく伝わらず、付け根の関節が痛いと困り顔。
そう。この「1の指の付け根が何歳になってもへこんだまま」というのも悩みの種でした。親御さんも困り顔。もう何回言っても変な持ち方に戻ってしまって……と。
やっぱり、最初が肝心。正しい持ち方が保てるまでよく観察して見守ることが大事。1の指も、正しく鉛筆を持つことで鍛えられることでしょう。綺麗に書けることは楽しいことだと教えてくれるこのワークがあれば、まだまだ希望が持てるぞ!うおー!!と叫びたいようなこの晴れやかな気持ち、皆さんに伝われー!!
2025.9.29 豊永泰子
みなさん、いかがだったでしょうか?
豊永さん、臨場感伝わるレポート、ありがとうございました。
このセミナーの配信は、10月1日から11月30日まで。
実際にご覧いただきながら、動画でしか伝わらない部分もご覧いただければ幸いです。
配信:プレ・ピアノ かくワーク①②発刊記念セミナー
配信期間:10/1〜11/30
info1@pianoland.co.jp
03-5742-7542